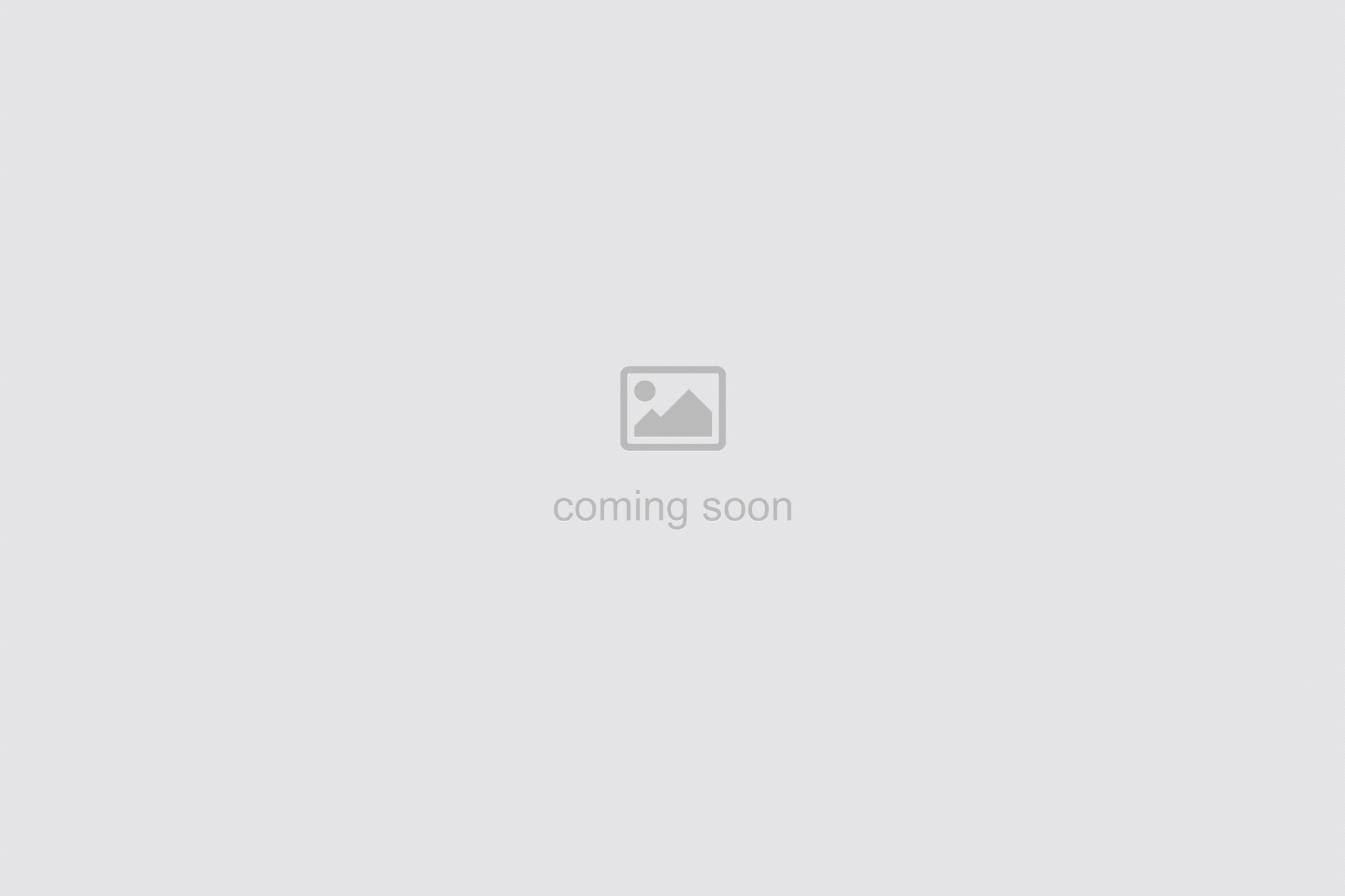一口メモ
一口メモ
一口メモ・高井流 ユニットケア談義 シリーズ50
2013-02-04
一口メモ・ユニットケア談義 シリーズ50
≪起床は目覚めた人から≫
早朝、私は6時50分過ぎに自宅を出て職場のぽふらとなみきに向かいます。自宅から職場まで35㎞、約45分要しますが、巨椋インターから瀬田東迄約19㎞は高速道路です。7時30分頃に職場に着くと、直ぐにぽぷらとなみきの11あるユニットを巡回するのですが、ひとり勤務で食事介助をしている職員を見ますと心から「お疲れ様」と思いながら朝の挨拶をします。最近各ユニットを見て回ると各ユニット11丁目を除いてほとんどの入居者が食卓に着いておられるのを見て、眠っている入居者を順番に訪室して起床していないか、と心配になるのです。昨年の8月21日の「一口メモ」でも書きましたが、起床のために順番に訪室し、眠っている入居者迄、覚醒させ着替えて起床して朝食を食べて貰うというのはユニットケアではないのです。目覚めた人から順に起床援助するのがユニットケアの個別ケアなのです。8月21日の一口メモを再掲しますので、各ユニットで再確認して欲しいと思います。
≪一斉の朝食からの卒業を≫
ユニットリビングにはぽぷらの場合7人、8人の入居者が、あるいはユニットの全員10人がテーブルを囲んで食事をしている光景を見ます。なみきの各ユニットは全ての入居者が食事をしていたり、既に食事を終えている入居者が出そろっていたりします。2人以上の職員がいる場合はあまり思わないのですが、1人勤務で食事のお世話をしている職員を見ると「ユニット型特養の弊害」を感じます。1人の職員で10人の介護をしなければならない時間帯がどうしてもあるのです。1人勤務の場合、それは「職員は心身とも疲れるだろう」と云う思いと、「見守りや介助は大丈夫だろうか」と云う不安な気持ちに私はなるのです。
かって私が介護職員をしていた20年程前のことですが、その時は個別ケアなどと云う語句はなく、食事に関しては三食とも「一斉が当たり前」になっていました。
例えば朝食については、早朝5時からの排泄介助を二人の夜勤者で行い順次、入居者を車椅子離床してもらい朝食の始まる午前7時30分まで待ってもらっていたのです。ですから早い人は2時間半も朝食が始まるまで待たせるというようなことをしていたのです。早出が午前7時に2名出勤して来ていましたからから、夜勤者と併せて4人で朝食準備を始めるのが7時頃です。その時には早出で出勤した職員が50名の入居者が全員と云って良い大半の入居者が大食堂に移動介助して集まっていました。そして7時半から朝食です。何でも一斉の介助で「介護」と呼ぶことの出来ない職員の都合に合わせ、職員が決めた職員本位の介助をしていたと今、深く反省しています。
当時の私は、個々の入居者が自然と目覚めた頃を見計らい離床、そして食事と云うような個別ケアとは程遠いことをしていたのです。7~10人の入居者の食事のお世話を1人の職員が食事介助をしながら、見守りなんて、ゆとりを持って出来るとはとても思えないのです。「本当にユニットの10人のお年寄りが、自然と目覚め、そして食事を順番にされているのか」と疑ってしまう私は邪推しているのでしょうか。馴染みの関係の構築とも関係のない取り組みだと思うのです。
また、別のユニットは2~3人の入居者が朝食を摂られていて、7~8人の準備されたトレイがユニットシンクに並んでいるのを見ますと、何故か安心できるのです。
ユニットケアは個別ケアです。ぽぷらとなみきの基本運営理念は「自然な暮らしの継続」です。入居者は「自然と目覚め、そして離床の援助を受け、朝食を日々摂られているのか、の点検と確認を今一度、各ユニットですることも必要ではないかと思うのです。